
最終更新日:2025.7.3
東京でいえば裏原宿のような雰囲気がある今泉エリア。繁華街である中洲や警固から徒歩圏内で、若者が多く集まる天神は目と鼻の先。道幅は広くないが、綺麗な店舗や雰囲気があるカフェなどが立ち並ぶ中で、『FIDES』の看板が目に留まる。シンプルな店内の四方には小林が手掛けた服やパンツ、アイテムが並ぶ。
少し店内で服を見ていると、小林がやってきた。共通の知人を経て今回の約束を取ったために、しっかりと話すのはこれが初めてだった。挨拶を済ませ、近くのカフェに移動してインタビューを始めると、そこには冷静に物事を見つめながらも、内に秘めた凄まじい情熱が感じとれた。
「人それぞれあると思いますが、遅かれ早かれアスリートをやっていると、どこかで引退という現実がやってきて、そこから職種が変わることが多い。第二の人生というより、これまで培ってきたものの上に新たなチャレンジをするという、完全に切り離したものではなくて、延長線上にありながらも、やっていることは全然違うという感覚を持っています」

セカンドキャリアをどう捉えているかという質問の答えだった。彼が言うように、セカンドキャリアは決して自分が生まれ変わるわけではなく、これまで自分が積み上げてきたものを活用しながら、信念を持ち続けた状態でこれまでとは別のことをするという捉え方もある。
もちろん、プロサッカー選手としての寿命が短かった選手は、プロ生活で成功できなかった悔しさをバネに新たなステージで新しい自分を追い求めることは重要なことだ。だが、彼のように15年間、しかもその大半をJ1リーグで過ごしてきた選手は、他の全く違う誰かになるのではなく、積み上げてきた実績と自信、経験をベースに「自分は自分」のままで舞台を移すという感覚が重要になる。
では、小林にとってプロの15年間を通して何を学び、どんな自分を作り出していったのか。
「最初はアマチュア契約に近い形で当時J1のジェフユナイテッド市原(現・ジェフユナイテッド市原・千葉)にギリギリ入った身分だったので、1年、1年、この世界で生き残っていくためにはどうしたらいいかを常に考え続けてきたプロキャリアでした。
『自分は才能がある選手とは違う』と理解さえしていれば、生き残っていく手段はいくらでもあると思います。僕にとってその手段は日常の過ごし方を逆算することでした。今日、1週間という時間を漠然と過ごすのではなく、その時々の明確な短期目標、長期目標を持って逆算しながら物事に取り組むなど、周りに流されずに自分で高い意識を持ってやることを大事にしました。
やっぱり自分の身の丈を知ると言うか、己を知るために何をすべきか。小さい頃から人の行動を見て考えることも多かったので、時には参考にしたり、時には反面教師にしたりしながら、自分というものを作り上げていきました」
自身は決してサッカーエリートではない。1979年6月20日に茨城県で生まれ育った小林は、中学時代の恩師に勧められて茨城県立波崎柳川高に進学。チームとしては全国大会には出られなかったが、国体に出場するなどサイズのあるDFとして頭角を現し、卒業後は大学サッカー界の名門・駒澤大学進学を手にした。駒澤大では1学年下に巻誠一郎、深井正樹が、2学年下には那須大亮らがおり、まさに隆盛期を支えた。
「高校の頃から本当に足元が下手で、周りにうまい選手がいる中で自分が生き残っていくためには、ヘディングで誰にも負けないようにするしか道はなかった。大学に入ってからはさらに周りのレベルが上がった中で、それでも僕はヘディングだったら誰にも負けなかったし、CBとして試合に使ってもらった。そこで『自分の生きる道はこれだ』と確信したんです。プロサッカー選手には中学生の頃からずっとなりたいと本気で思っていたからこそ、下手くそな自分がその舞台に行くためにはどうしたらいいかを本気で考えていたことがプロになれた要因だと思います」
自分の現在地を理解した上で、上の世界にチャレンジしていく精神は自然と磨かれていた。プロになってからの1年半はリーグ戦出場こそ叶わなかったが、2003年8月に当時J2の山形に期限つき移籍をすると、待望のJリーグデビューとプロ初ゴールをマーク。完全移籍に切り替わった2004年には山形で不動の存在となった。2006年に当時J2だった神戸に移籍をし、その年にJ1昇格を果たすと、それ以降のサッカー人生は神戸、甲府、鳥栖とすべてJ1リーグで戦った。
着実にプロとしてのキャリアを積み上げていく中で、ある感情が彼の中で湧き上がってきた。

「若手の頃はこの世界で成り上がってやる、這い上がってやるという野望が原動力となっていて、他のことは考えていませんでした。でも、プロ7年目の30歳を過ぎてくると徐々に頭の中で『次、どうしようかな』と考えるようになりました。そこから引退までの5年間、1年、1年が勝負だという気持ちはルーキー時代から一切変わらないのですが、『いずれ終わりが来る』というどこか冷静に自分を見る目がありました」
プロサッカー選手の寿命はただでさえ短く、30代に入れば多くのアスリートが引退の2文字が頭をよぎり、その先のセカンドキャリアに対する不安も生まれてくる。小林も例外ではなかった。
この不安はマイナスなことばかりではなかった。むしろ、彼はこの感情をポジティブなものに変えたのだった。
まず彼がベースに置いたのは、サッカーはこれまで通り全身全霊でやるべきことを精一杯やるということだった。
J1という第一線で戦っている中で、不安に感じるからと言って具体的な準備を始める余裕もないし、具体的なヴィジョンを持てる状況ではない。そこで無理にセカンドキャリアに対する時間を割いてしまうと、結果としてサッカーにコミットする力が薄れてしまい、パフォーマンスが落ちて、プロのキャリアを続けたくても続けられない本末転倒な状況に陥ってしまう。
彼は常にサッカーのことを真剣に考えて、1日の練習でも練習時間より早くクラブハウスに行き準備をして、練習後もケアなどで時間を費やした。同時にサッカーにコミットする時間以外を有効活用した。もともとサッカー界以外の人たちと食事に行ったり、交流したりすることは苦ではなかったが、より外の世界を学ぶべく、いろいろな人と会ってコミュニケーションをとるようになった。
突然沸き起こった将来への不安が、逆に小林にとってはそこから5年間プロのキャリアを重ね、引退後すぐにアパレル業界に飛び込んだ重要な原動力となったのだった。
では、なぜ彼はセカンドキャリアにアパレルを選んだのか。そして、なぜ店舗を構えるという逃げ道のない大きなリスクを持って挑んだのか。その理由を紐解いていく。
中編はこちらからご覧ください。

小林久晃(こばやし てるあき)
茨城県出身の元プロサッカー選手。ポジションはDF。
駒澤大学を卒業後、2002年にジェフユナイテッド市原(現・ジェフユナイテッド市原・千葉)へ入団。以降は、モンテディオ山形、ヴィッセル神戸、ヴァンフォーレ甲府でプレーしたのち、2012年にサガン鳥栖へ加入。2016年12月9日現役引退を発表し、15年のプロキャリアに幕を閉じる。
引退後の2017年にアパレルブランド「FIDES(フィデス)」2022年に「FIDES GOLF」を立ち上げ、福岡・今泉の直営店、ECなどで展開。元プロサッカー選手のキャリアや人脈を活かし、アスリートの支持を集める。
director / editor : Yuya Karube
assistant : Hinako Murata / Makoto Kadoya / Naoko Kamada

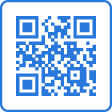
RECOMMENDおすすめ記事
- Career2025.7.3

 【中編】信頼を築くのは人生そのもの。プロ15年間の延長線で小林久晃が勝ち取ってきたFIDES(信頼)【中編】信頼を築くのは人生そのもの。プロ15年間の延長線で小林久晃が勝ち取ってきたFID
【中編】信頼を築くのは人生そのもの。プロ15年間の延長線で小林久晃が勝ち取ってきたFIDES(信頼)【中編】信頼を築くのは人生そのもの。プロ15年間の延長線で小林久晃が勝ち取ってきたFID - Career2025.5.30

 【前編】努力もリスクを負うこともできなかった高卒Jリーガー平秀斗が、牛に全力コミットする経営者になる【前編】努力もリスクを負うこともできなかった高卒Jリーガー平秀斗が、牛に全力コミットする
【前編】努力もリスクを負うこともできなかった高卒Jリーガー平秀斗が、牛に全力コミットする経営者になる【前編】努力もリスクを負うこともできなかった高卒Jリーガー平秀斗が、牛に全力コミットする - Special2024.11.25

 リンクアット・ジャパンが未経験でもアスリートを信じ、採用したい理由。競技生活後のキャリアにも広大なフリンクアット・ジャパンが未経験でもアスリートを信じ、採用したい理由。競技生活後のキャリア
リンクアット・ジャパンが未経験でもアスリートを信じ、採用したい理由。競技生活後のキャリアにも広大なフリンクアット・ジャパンが未経験でもアスリートを信じ、採用したい理由。競技生活後のキャリア - Special2024.6.26

 【前編】「引退」など考える必要はない。人生を組み上げる起業家兼現役アスリート小谷光毅の軸の作り方【前編】「引退」など考える必要はない。人生を組み上げる起業家兼現役アスリート小谷光毅の軸
【前編】「引退」など考える必要はない。人生を組み上げる起業家兼現役アスリート小谷光毅の軸の作り方【前編】「引退」など考える必要はない。人生を組み上げる起業家兼現役アスリート小谷光毅の軸



