
最終更新日:2024.8.30
前編はこちらからご覧ください。
志半ば、理想と現実の大きなギャップを感じながらスパイクを脱いだ彼には、これ以上サッカーの世界で生きていくことすらも限界に感じていた。
「高校の最後の大会、プロシーズンの始まりが華やかだったけど、その後はもう華やかさとはかけ離れていったというか、かつての仲間たちがどんどん羽ばたいている現実に対して、『俺は何をやっているんだ』と言う気持ちが日に日に強くなっていた。
でも、その一方で高校を卒業してプロになって、サッカーだけで、社会のことを全然知らなかった自分も徐々に不安感を抱くようになりました」
早く見切りをつけてセカンドキャリアに進んだ方がいい。そう思う一方で、彼の中でサッカーに対するネガティブな感情があったのも事実だった。
「何より一番はサッカーから離れたかったんです。コーチとかサッカー関連には進みたくはなかった。そうなると一般企業に就職するしか道はなかった」
複雑な思いが入り混じる中で、とりあえず決意は固まった。だが、ここで新たな疑問が浮かぶ。
「じゃあ、今の俺に何ができるのか」

サッカー以外に特殊な技術を持っているわけではない、資格を持っているわけでもない。サッカー以外で自分は何が得意で何が不得意かも分からない。ただ1つわかっているのは『世間知らず』ということだけ。それが当時の彼を突き動かした。
「まずは世間を知ろうと。ちょうど知り合いに携帯電話関連の営業職をやっている人がいて、その人の紹介で営業をやろうと思いました。自分は営業が得意か不得意かは分からなかったけど、とりあえずサラリーマンとして働いてみようと」
ユニフォームからスーツに着替えて、いざ社会人生活がスタートした。しかし、そこで待っていたのは厳しすぎる現実と、何もできない自分の存在だった。
「マンションとか住宅街を1戸、1戸ピンポンを押して営業するんですが、当然得体の知れない人間がいきなり訪問してくるので、対応はみんな悪いじゃないですか。『何しにきたんや』、『用はない、とっとと帰れ』とも言われたし、明らかな居留守もあった。もうかなりそれが衝撃的でした。今までそんなことを言われたことがなかったし、自分が訪問をして嫌な顔をされたこと自体初めての経験だった」
これまではプロサッカー選手がやって来たということで、みんなが笑顔になっていた。それが当たり前だったのに、一気に冷たい視線に切り替わった。
話を聞いてくれる人もいたが、いざ自分たちの会社の商品やメーカーの切り替えなどの具体的な話をすると、言葉がうまく出てこず、会話が全く弾まない。
「この人にはどのような言い回し、言葉の強弱がいいのか。話をしながら『この展開ならどうするか』、『このワードをどこで入れようか』、『これに興味あるんねや、じゃあこれにこれを結びつけて話そう』と頭を常に働かせながら喋るのは本当に難しかった」
笑顔でいなきゃいけないのに、どんどん顔が引きつっていく。それが伝わってか、今まで話を聞く姿勢だった相手がどんどん冷たい態度に変わっていく。結果、営業をしてもなかなか成約には至らなかった。
「今思うと正直、自分の中で『これだけ長い間、競争の世界で生きてきたのだから、俺やったら一度経験をすればある程度できるだろう』という根拠のない自信を持ってしまって、自分を過信していた部分があった。でも、実際はそうじゃなくて、自分には話術もないし、営業のスキルもない。力のない自分にただ失望しただけだった」

自分の甘さに気づき、かつ持っていた自信もボロボロに崩れていった。しかし、ここで働くことを辞めたら、自分の生活自体ができなくなる。最初の会社は半年で辞めてしまったが、今度は電気系の会社に転職をして、再び営業職として働き続けた。
ここから彼は漠然とした時間を過ごすことになった。営業をやる以上、成果を求められ、そこが評価の決定的な軸になることは間違いない。だからこそ、青木は営業職をやっている高校時代の親友にお願いをして、訪問のシミュレーションや営業トークなどを徹底的に学んだ。その成果もあって、徐々に成約も貰えるようになった。
しかし、結果が出始めても消えないモヤモヤがあった。
「どれだけ成約を勝ち取っても達成感というか、爽快感などが湧かないんです。もちろんその瞬間は『やった』と思うのですが、家に帰ると『俺、何やっているんだろう』と落ち込む日が続きました」
ゴールを決めた喜び、試合に勝利した喜びは今もはっきりと覚えている。しかし、営業で結果を出してもあの喜びには到底達しない。それでも明日はやってくるし、生活をするために仕事をする時間は一切待ってくれない。
「ただ毎日を必死でこなしているだけだった」
どんどん生まれていく虚無感。これこそがセカンドキャリアで苦心するアスリートたちの最大の問題の1つである。
人間は一度感情を爆発させた瞬間や、全身で喜びを感じた瞬間は記憶に深く刻まれる。プロのアスリートはそうした瞬間が他の業種の人たちよりも多く、かつスタジアムや大きな大会ではとてつもない注目度の中で体験する。
日常からかなりかけ離れた刺激的な体験を刻むことができるのはいわば「プロアスリートの特権」だろう。しかし、それが引退後に一気に失ってしまう。プロアスリートの非日常は現役を続けない限り、味わう機会はそうそう無いに違いない。
だからこそ、その競技の指導者になったり、関係者になったりすることで、間接的にでもその感情を味わおうとする人が多くなるのも事実だ。青木のようにその競技そのものから離れた時に、機会が少なくなるどころか、無くなったと感じることは無理もない。
「社会のことは学べていると思うし、経験を積めている実感はあるけど、ただそれだけ。不幸せでは無いけど、毎日に彩りがなかった。ずっとサッカーの世界にいたから、あのエモーショナルな瞬間は一生忘れられないし、サッカーを辞めたらなかなか味わえないものであることも理解していました。

でも、どこかでどうしてもそれを求めている自分がいました。なので『今の仕事が俺の人生をかけてやるものではないな』と思うようになりました。でも次に人生をかけられるものなんてそうそう現れるものじゃない。この時期は調子乗り世代に対する劣等感が現役時代より膨らんでいきました。
サッカー選手としてではなく、人生としての劣等感。それに打ち勝つにはサッカー選手時代のような達成感と爽快感しか自分を満たせるものがなかったと思います。でも、達成感・爽快感を自分で得られる『なにか』がなかなか見つからなかった。その現実に愕然としていました」
社会人として4年間も経験を積んでも、見えてくるはずだった自分の本来の姿は一向に見えてこない。暗闇の中を必死でもがいて前に進もうとする彼に、大きな光をもたらしたのは、『偶然の転機』だった-。
後編はこちらからご覧ください。

青木孝太(あおき こうた)
滋賀県出身の元プロサッカー選手。ポジションはFW。
2005年の第84回全国高校サッカー選手権大会で、当時2年生だった乾貴士を擁して『セクシーフットボール旋風』を巻き起こし、初優勝を飾った野洲高校のエースストライカーである。高校を卒業後の2006年にジェフユナイテッド千葉へ入団。その後、ファジアーノ岡山、ヴァンフォーレ甲府、ザスパクサツ群馬を渡り歩き、2014年シーズンをもって現役を引退した。
引退後はサッカー界から離れ、一般企業に就職。2020年より親族経営の電気工事会社に入社。電気工事士として従事している。
editor : Takushi Yanagawa
director : Yuya Karube
assistant : Naoko Yamase
金本竜市

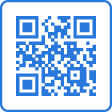
RECOMMENDおすすめ記事
- Career2024.8.30

 【後編】あの素晴らしい瞬間はどこにある?『調子乗り世代』青木孝太が「セクシーフットボール」と同じ感動【後編】あの素晴らしい瞬間はどこにある?『調子乗り世代』青木孝太が「セクシーフットボール
【後編】あの素晴らしい瞬間はどこにある?『調子乗り世代』青木孝太が「セクシーフットボール」と同じ感動【後編】あの素晴らしい瞬間はどこにある?『調子乗り世代』青木孝太が「セクシーフットボール - Learning2023.10.11

 【前編】“育成の水戸”ホーリーホックは競技力だけを扱わない。アスリートがウェルビーイングを目指すべき【前編】“育成の水戸”ホーリーホックは競技力だけを扱わない。アスリートがウェルビーイング
【前編】“育成の水戸”ホーリーホックは競技力だけを扱わない。アスリートがウェルビーイングを目指すべき【前編】“育成の水戸”ホーリーホックは競技力だけを扱わない。アスリートがウェルビーイング - Career2023.3.10

 【前編】「アスリートとして死んだ自分」をどう活かすか。引退、復帰、会社員を経たオリンピック選手が語る【前編】「アスリートとして死んだ自分」をどう活かすか。引退、復帰、会社員を経たオリンピッ
【前編】「アスリートとして死んだ自分」をどう活かすか。引退、復帰、会社員を経たオリンピック選手が語る【前編】「アスリートとして死んだ自分」をどう活かすか。引退、復帰、会社員を経たオリンピッ



