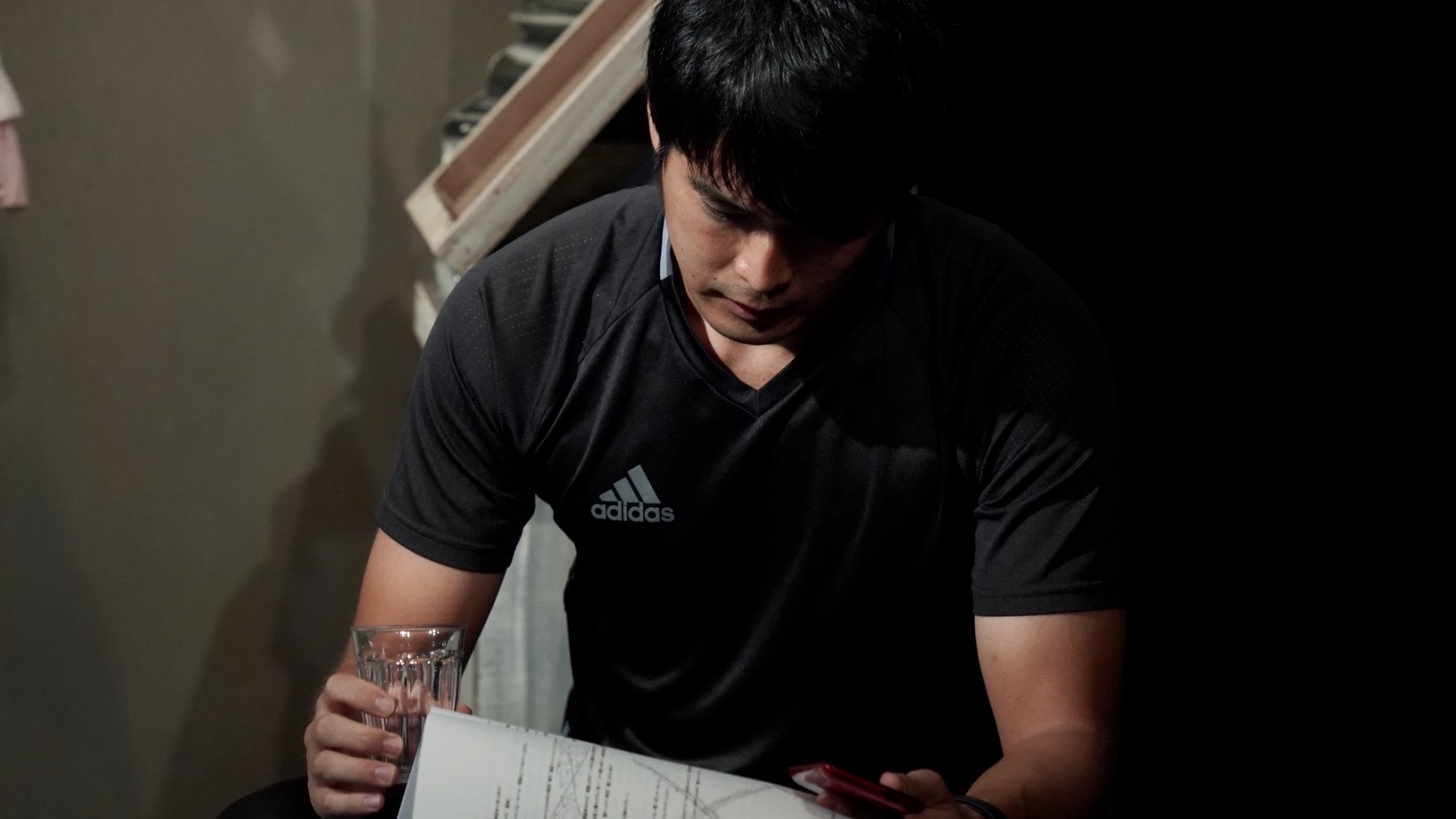
最終更新日:2023.10.17
前編はこちらからご覧ください。
1からのスタート。分かってはいたが、青山を待ち構えていたのは明確な序列という厳しい現実だった。俳優になってみると、『元Jリーガー』という肩書は一切通用しなかった。
『新宿スワンⅡ』の役柄は、主人公である白鳥龍彦(綾野剛)に絡むチンピラ役だった。撮影は寒さが厳しい2月。15時半にロケ場所の港に集合するが、当然控え室はない。主要役柄を務める俳優たちには複数のスタッフがつき、簡易的な休憩所にいるのに対し、青山らは吹きさらしの中で出番を待ち続けた。

一向にやってこない出番。椅子もなく、寒さで身体がブルブルと震えていたが、周りのスタッフからは放っておかれた。やっと出番のシーンが来たと思ったら、あっという間に撮影が終わる。セリフも当然ない。一瞬で出番が終わり、メインの役者には話しかけることも許されなかった。15時半に入った現場を離れたのは翌日の早朝のことで、最後も監督やスタッフからの挨拶はなく、そのまま帰宅した。
「序列」と言う名の大きな溝を目の当たりにした。ここで青山は大事なことに気づく。思えば、プロサッカー選手としての自分は「至れり尽せり」の環境にいたのだと。
10代の頃から練習着はスタッフが洗ってくれて、綺麗にたたまれ、練習場に行けば当たり前のように手入れされた芝生のピッチとボール、スパイクを履いてプレーできた。ファンが練習場に詰めかけ、サインを求められ、いい車にも乗ることができた。それが今は所詮1人の駆け出しの俳優に過ぎず、世話をしてくれる人もいない。
「職種は全然違いますが、『あ、俺ってこれまでめちゃくちゃ恵まれていたんだな』と痛感しました。もちろん当時も周りのスタッフへの感謝の気持ちは持ち続けていたけど、自分が思っていた以上にとんでもなくありがたいことをされていたなと」
同時に心の奥底から湧き上がる気持ちにも気づくことができた。「多くのスタッフに囲まれている綾野剛さんや浅野忠信さんを見て、『俺もここから這い上がってメジャーになりたい、主役になりたい』と、野心というか、向上心が生まれてきたんです」
それは彼の心の中から枯渇してしまっていた感情だった。エモーショナルになっている自分が何よりも嬉しかった。
「懐かしい感情でした。僕もユースのときはトップ選手たちを見て『報道陣に囲まれて、高級車に乗って凄いな…。早くあんな風になりたいな』と憧れていた。あのときの感情に戻れた気がしたんです」
もちろん、叔母から言われた通り、俳優の世界は甘くはなかった。なかなか仕事が決まらない。オーディションの話もほとんどなかった。それでも毎日が充実していた。
年収も0に近い状態に落ちた。ただ、選手時代から派手にお金を使うことがなかったこともあり、倹約をしながらであれば生活をすることはできた。
転身1年目には町中華で人生初めてのバイトをした。10代の高校生や大学生のバイト仲間に、「青山さんって本当に何もできないんですね」と言われることもあったという。それでも「バイトなんてしたことがなかったし、実際にわからないことばかりだったから、とても新鮮だった」となんの不満もなく1年間働き通した。
2年目、少しずつ俳優としての仕事が入るようになったが、それでも演技だけでご飯を食べられるレベルではない。選手時代の貯金を切り崩しながら生活し、マンションも1年目に契約をした少し高い場所から身の丈にあった場所に引っ越した。
「落ちぶれたとか、惨めだとかは一切思いませんでした。そもそも何もない状態で選んだ道だから、こうなることは分かっていたし、覚悟の上でした」
ただ、月日が経つにつれ、自分の甘さも感じるようになった。
「事務所にスムーズに入れたことで、僕の気持ちのどこかで『待っていれば仕事は来るだろう』と言う甘い考えが生まれていました。もっと自分から積極的にいかないと何も掴めないと危機感を覚えるようになりました」
サッカーと同じで、俳優も自らの力で掴み取りにいかないと成長をしないし、成果も得られない。ただ、全くの素人がゆえにノウハウもまだ掴めておらず、何より演技の楽しさはまだ見出せないでいた。
「自分は演技において何が持ち味なのか。それをどう発揮すればいいのか。この世界は丁寧に教えてもらえるわけではなくて、自分で工夫して、努力をして見つけて、仕事を掴んでいく必要がある。ただ、サッカーの時と違って自分の武器を見出せなかったんです」

同時に周りからの冷たい目線にも苦しんだ。周りからは「お前はいいよな、七光りがあって」、「元プロサッカー選手だから仕事をもらえると思うなよ」など辛辣な言葉を浴びることもあった。同じ舞台に出演した役者からも「お金あるのになんでこんな舞台に出演しているの」と言われたり、2年目以降は町中華ではなく、サッカースクールを指導するバイトを始めていたこともあり、「君はいいよね、俳優業でダメでもサッカーで仕事があって」と皮肉を言われたりすることもあった。
「現場に入っても役の大小関係なく、あまり相手にされていないように感じることが多かったんです。いてもいなくても良いというか基本的に僕に興味がないと感じることが多くて、存在感を放てない自分がいました」
悔しかった。舞台やドラマなどの仕事は入るが、同じプロデューサーや制作チームから「もう一度使いたい」という『おかわり』が来ない。その現状と相まって、だんだん彼の心の中で『プロサッカー選手だった自分』を無理矢理遠ざけようとしてしまった。
「俺はサッカーにすがっていない。でも、周りからそう見られてしまっているのなら、それではいけない。俺はあくまでゼロからのスタートをしているんだ」
彼は低姿勢を貫いた。だが、これは自分の持ち味を消してしまうことにつながってしまっていた。
プロサッカー選手というキャリアは、多くの人が持ちたくても持てないキャリアだ。それを持っている時点で、大きなアドバンテージであるし、プロの厳しい世界での経験は必ず次なるステージでも活きる。いや、死ぬまで自分の土台として活き続ける。むしろセカンドキャリアに進んだからこそ、その経験やキャリアをうまく活用しないと、本当の意味でのステップアップは成しえない。
彼はあまりにもセカンドキャリアを『ゼロからのスタート』と強く位置付けすぎていた。周囲からの嫌味や批判は、よりその思いに彼を囚わせ、自分らしさを見失わせていたのだった。
その事実を教えてくれたのが、いまの彼がひょんなことから繋がった元ブラジル代表のエジミウソンだった。2002年の日韓ワールドカップの優勝メンバーであり、かつてバルセロナでも活躍をした名手。そんなエジミウソンがブラジルで恵まれない子供たちを対象にした財団を立ち上げ、日本でも財団活動を展開することになったことで、そのサポート役として日本の理事として関わるようになったのだった。

エジミウソンに今の状況を相談した時、「ゼロからのスタートのつもりで役者をやっています」と伝えると、彼の口から帰ってきた言葉に青山は心を大きく揺さぶられた。
「お前がサッカーに捧げた20年間は一体何だったんだ?何でそのキャリアを切り離す必要がある。切り離そうとする考えを持っているお前自身が調子に乗っている。何様なんだ!」
真剣な表情でエジミウソンはこう続けた。
「確かに今やっていることは新しいことかもしれない。でも、それをまたゼロからやるって、お前は赤ちゃんか?俺には意味がわからない。お前はサッカーを通じて悔しい思いだったり、喜びだったり、努力することの尊さ、仲間との絆などいろんな人生において大切なことを経験してきたのに、なぜそれをゼロにする必要があるんだ?元サッカー選手でいいじゃないか。それはお前しか持っていない大きな武器だぞ、自信を持て。大事なのは新しい取り組みだからこそ、常に学ぶ気持ちを持ってやり続けること。ゼロからやるなんて、それは自分自身のこれまでの人生を否定しているし、それこそサッカーに対する冒涜だぞ」
この言葉は心の奥底にまで響いた。プロサッカー選手としての経験は「過去の栄光」ではなく、自分自身を形成する上で大切なものであり、自分の土台。そこに気づいたことで、徐々に青山の意識は変わっていった。
「サッカーに例えたら、残り数分でチャンスを与えられて、そこで結果を残せなかったら次がないというのと同じ。いかに少ない時間でも、すんなりと試合の流れに乗って、チームのためにプレーしながら自分を出しきれるか。演技もサッカーも同じだなと思うようになりました」
オーディションや演技の時に、サッカーとリンクさせながら、どうメンタルを整えるか、どう立ち向かうかをイメージできるようになった。新たな学びと経験則をつなぎ合わせながら俳優業に打ち込むことで、徐々に自分のスタイルが見えてくるようになった。
そして2020年、彼に転機が訪れた。新しいマネージャーが担当になると、ここから二人三脚で仕事に打ち込むようになった。マネージャーは顔合わせの時から厳しく接する一方で、自分を理解してくれようとする姿勢が伝わった。
「この人なら本音をぶつけられる」と青山はこれまでの思いの全てをマネージャーに打ち明けた。二人三脚で歩んでいくことを決めた中で、「俳優の深さ、楽しさを教えてもらった」と語る上西雄大監督と出 会った。
「『ヌーのコインロッカーは使用禁止』という上西さんが手がける舞台に出演した時、上西さんの演技指導が僕に響いたんです。稽古で『今どういう気持ちでやったの?』『誰に向けてセリフを言ったの?』と細かく指導をしてくれたんです」
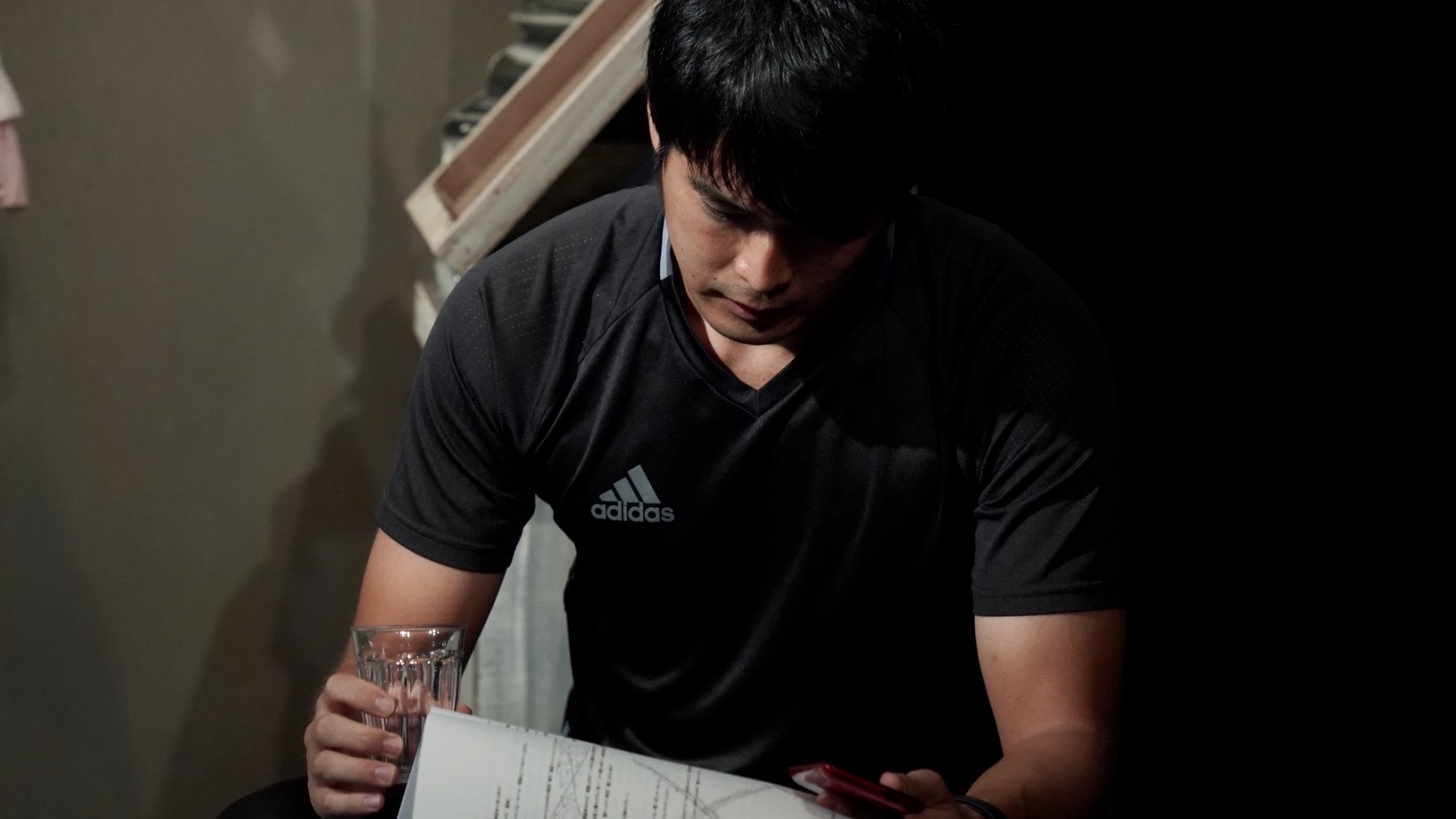
今まではそこまで細かく演技指導されることはなかった。だからこそ、発見の連続だった。
「他の演者さんに対する指導にも耳を傾けると、『なるほど、こういうことだったのか』とこれまで疑問に思っていたことが解決していく。もう毎日が学びと発見があったし、これまでの舞台やドラマを振り返っても『あの時こういうことを言っていたんだ』とつながっていって、演技や表現の深さをようやく理解できたんです」
これによってオーディションへの向き合い方もガラッと変わった。これまではマネージャーがとってくるオーディションをただ受けていたが、最初のエントリーの段階でよりプロフィールを工夫して、監督がどのような役を、そして人材を求めているのか考えるようになった。
どんどん変化をしていく自分の心。俳優としての自覚が芽生えていくにつれ、叔母・篠ひろ子、叔父・伊集院静の言葉の本当の意味を知った。
「最初は私も演技が出来なかった。でも『なにくそ精神』で絶対にいつか見返してやるという気持ちを常に持っていたよ。売れてからも演技力や表現力よりも、『人としてのあり方』がそれらに反映されるから、常に謙虚と感謝の気持ちを持って、少しでも人から応援されるようにしなさい。芸能は他の職種の人たちとやっていることは変わらない。でも、ちょっとだけ他の職種よりスポットライトを浴びているだけで、同じ人間なのだから決して驕ってはいけない。そんな態度を取る時点で人としてダメよ」
篠からは役者としての心構え、謙虚で応援される人でありなさいと人として大切なものを教えてもらった。
「スポーツ選手の会話や返しをそのままやっていていい世界ではないから、ちゃんと言葉を考えて発しなさい。より目上の人と会うのだからこそ、これまで以上に明確な言葉で伝えないといけないよ」
伊集院からは言葉遣いの大切さ、礼節を学んだ。
「2人には全部見透かされている気がしますね。2人の言葉とエジミウソンの言葉を合わせると、サッカーと俳優はちょっと似ているところがあって。パスでも受け手へのメッセージを送るじゃないですか。チームプレーもそう。常に周りにメッセージを送るプレーや演技をしないといけないし、それらで観客を魅了しないといけない。それでいて周りへの感謝の気持ちを持って真摯に取り組まないといけない。人生って、一本の線で繋がっているんですよね」
青山隼の生き方を見て、筆者は一つの教訓を得た。それは「『自分は自分』であり、それ以外の何かにはなれない」ということだ。
自分の過去に対して強制的に蓋を被せようとすることで、時には心のリセットができるかもしれない。だが、それに躍起になってしまうと自己否定に繋がる危険性も孕んでいる。
青山は心ない人間から「あいつは自分の経歴を利用している」と言われてしまうこともあるという。しかし、彼が築いた経歴は簡単に手に入るものではない。真摯にサッカーに打ち込み、ストイックかつ向上心を持って弛まぬ努力をして来た結果、掴みとった『かけがえのない財産』なのだ。
自らの力で掴み取ったもの、築き上げた自分と言うアイデンティティを否定したら、それは自分ではない存在になってしまう。セカンドキャリアは決して『ゼロからのスタート』ではなく、より自分の可能性を見出す積み重ねの一環であり、自分の可能性を広げる未来に向かった道のりであるのだ。
今、青山は苦しみを抜け、俳優としての人生に大きな意義とやりがいを見出して、他にはない唯一無二の武器を引っ提げて、自分らしくチャレンジを積み重ねている。
「今もずっとサッカーを好きでいられて幸せです。職業としてのプロサッカー選手を辞めただけで、サッカーは大好きだし、子供たちにサッカーを教えることも大好き。サッカーに関わっている自分も、舞台に立っている自分も、オーディションに臨んでいる自分も、全て僕なんです。全てがつながっているからこそ、演技に『人』が浮かび上がってくる。そう考えるとまだまだ伸びしろだらけだと思うので、これからより周りに感謝をしながら俳優として頑張っていきたいです」
青山の名を全国区にするような大きな仕事は、まだできていない。しかし、今やっていることはすべて未来にリンクする。その希望がある限り、彼が歩みを止めることは決してない。

青山 隼(あおやま じゅん)
1988年1月3日生まれ。宮城県仙台市出身の元プロサッカー選手。ポジションはMF。14歳以下の年代から日本代表に名を連ね、不動のボランチとして活躍した。
Jリーグでは正確なロングパスと、恵まれたフィジカルを生かしたタイトな守備、攻撃参加からのミドルシュートを武器に、名古屋グランパス、セレッソ大阪、徳島ヴォルティス、浦和レッズなどのクラブを渡り歩いた。2015年に現役引退を発表。
引退後はジャパン・ミュージックエンターテインメント所属の俳優として活躍している。
editor : Takushi Yanagawa
director : Yuya Karube
and my family

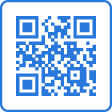
RECOMMENDおすすめ記事
- Career2023.9.13

 非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ選手経営者の非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ
非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ選手経営者の非合理的に見える選択も、長い目で見れば合理的。”あの日”魅せられた光景に導かれた元バスケ - Special2023.6.26

 【後編】半端にはしない覚悟で挑んだレッドオーシャンな飲食業。人気居酒屋に成長させた元バスケ選手の軌跡【後編】半端にはしない覚悟で挑んだレッドオーシャンな飲食業。人気居酒屋に成長させた元バス
【後編】半端にはしない覚悟で挑んだレッドオーシャンな飲食業。人気居酒屋に成長させた元バスケ選手の軌跡【後編】半端にはしない覚悟で挑んだレッドオーシャンな飲食業。人気居酒屋に成長させた元バス - Special2023.5.1

 【前編】一度は捨てた「過去の栄光」と拾い直した「元サッカー選手」 すべてを紡いでいく俳優・青山隼の挑【前編】一度は捨てた「過去の栄光」と拾い直した「元サッカー選手」 すべてを紡いでいく俳優
【前編】一度は捨てた「過去の栄光」と拾い直した「元サッカー選手」 すべてを紡いでいく俳優・青山隼の挑【前編】一度は捨てた「過去の栄光」と拾い直した「元サッカー選手」 すべてを紡いでいく俳優 - Special2023.4.10

 【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジェンド、そし【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジ
【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジェンド、そし【後編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジ - Special2023.4.10

 【前編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジェンド、そし【前編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジ
【前編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジェンド、そし【前編】「今」を必死で生きているか。中途半端と言われた日々に勝ち、ファジアーノ岡山のレジ


